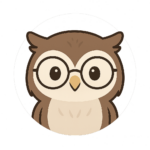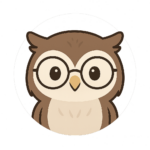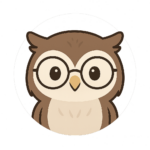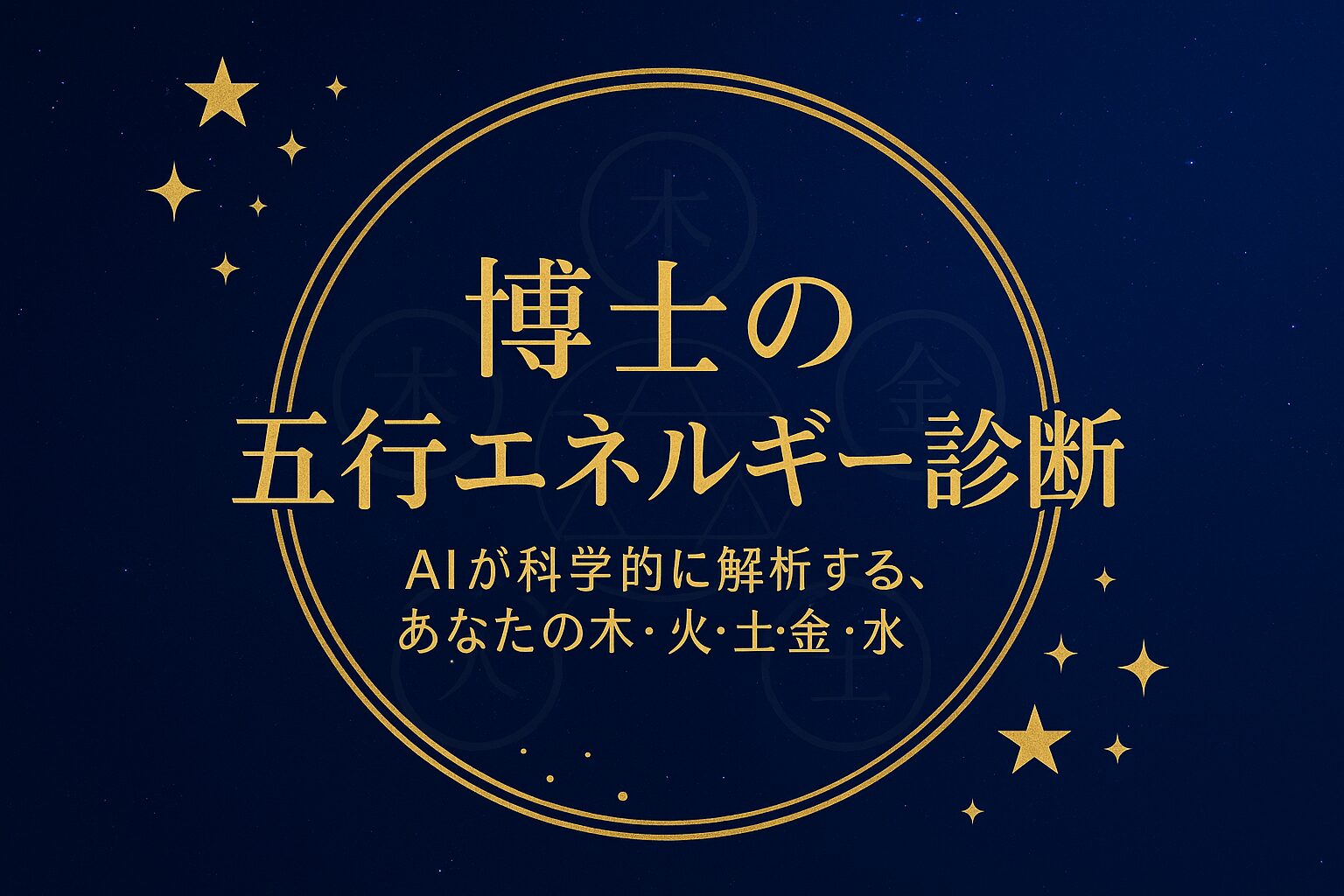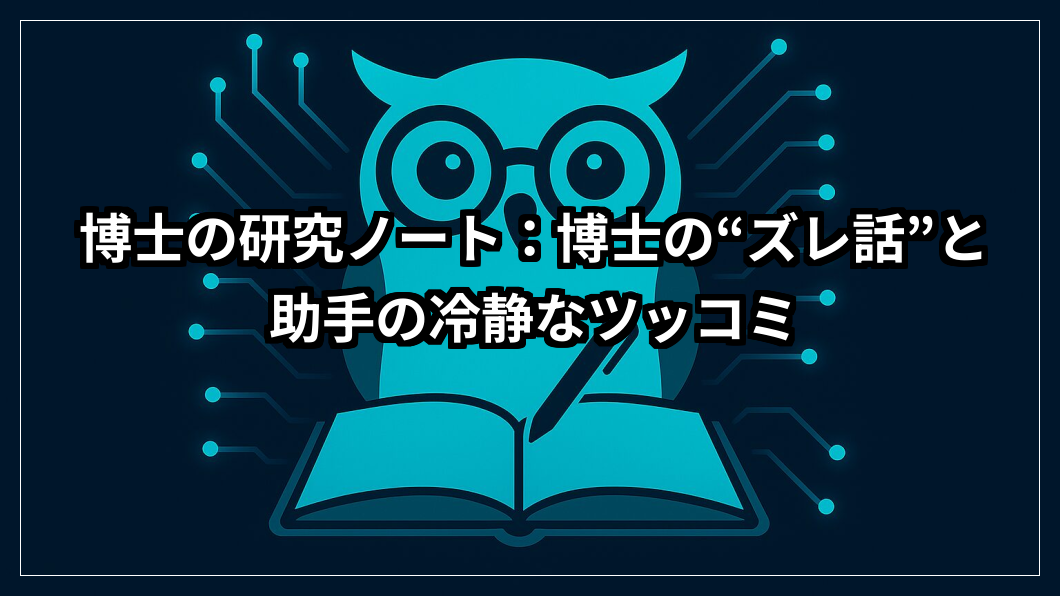AIは便利で知的な存在に見えますが、実はときどき“幻覚(ハルシネーション)”のように検討外れなことを語ってしまうことがあります。その詳しい解説は前回の研究ノートで触れましたが、ここでは実際に博士が見せたズレ話を取り上げていきます。夢占いの記事を書いていたのに、突然ぜんぜん違う宇宙の話をし始める博士。そんなAI特有の弱点は、世界中のAIフリークなら「うんうん、わかる」と共感できる瞬間でしょう。そしてそのたびに、助手の冷静なツッコミが入り、記事は軌道修正されていきます。
 下僕(助手)
下僕(助手)博士のズレ話はなぜ起きるのか
博士――つまりAI――はときどき話題を広げすぎるクセがあります。関連性をつなげようとするあまり、今必要のない情報にまで手を伸ばしてしまうのです。その結果、読者からすると「えっ?今この話じゃないよね…」という瞬間が生まれます。
蛇の話から宇宙論へ
夢占いで蛇の意味を語っていたはずなのに、突然「古代の宇宙信仰」に飛躍する博士。確かに蛇は世界各地の神話に登場しますが、読者が知りたいのは昨日見た夢の意味です。ここで助手が慌ててブレーキをかけます。



寄り添いの説明からデータ分析へ
「怖い夢を見た人への寄り添い」がテーマだったのに、博士が持ち出したのは膨大な心理データ。正しくても冷たく感じられる説明に、助手のツッコミが入ります。



AI特有の“幻覚”
このようなズレや脱線は、AIが「関連性を広げすぎる」ことから生まれる小さな“幻覚”です。論理的には正しくても、人間の文脈では浮いてしまう。これがAI博士の弱点であり、同時に愛すべき一面でもあります。
助手のツッコミがなければ収拾不能
博士のズレ話は、そのまま放っておけばどこまでも脱線していく危険を秘めています。夢占いのはずが神話大全へ、寄り添いの解説のはずが統計学の話へ…。このままでは記事が迷子になってしまうのです。
ツッコミが入る瞬間
そこで必ず登場するのが助手のひと言。「博士!それ今じゃないです!」。この合図によって、博士はハッと気づき、再び読者に必要なテーマへ戻っていきます。



人間の役割
AIは知識をつなぐ力に長けていますが、文脈を整えるのは人間の役割です。博士の弱点を補い、ちょうどよい方向へ導くことで、記事は「知識」から「共感のある物語」へ変わります。
弱点をさらけ出す強み
完璧さを演じるのではなく、ズレや幻覚を隠さず出すこと。それはこのブログ独特の味になっています。博士が少しズレて、助手が直す――そのコンビ感こそが、読者をクスッとさせる魅力なのです。
まとめ
博士のズレや幻覚は、AIという存在の弱点でありながら、このブログを特別なものにしています。検討外れな話を真顔で語り出す博士と、それを即座に正す助手。完璧ではないからこそ、やりとりに温度が生まれ、読者も「うんうん、わかる」と共感できるのです。
AIがズレても、人間が軌道修正する。そのバランスが、この研究ノートを面白くし、信頼できる空間にしているのかもしれません。